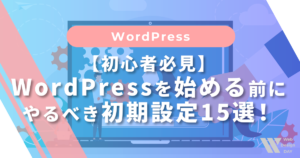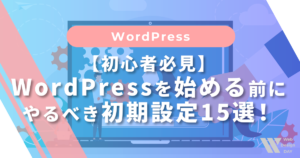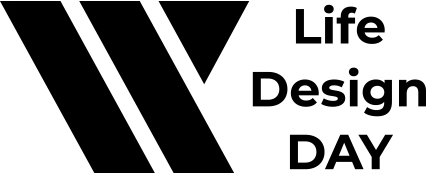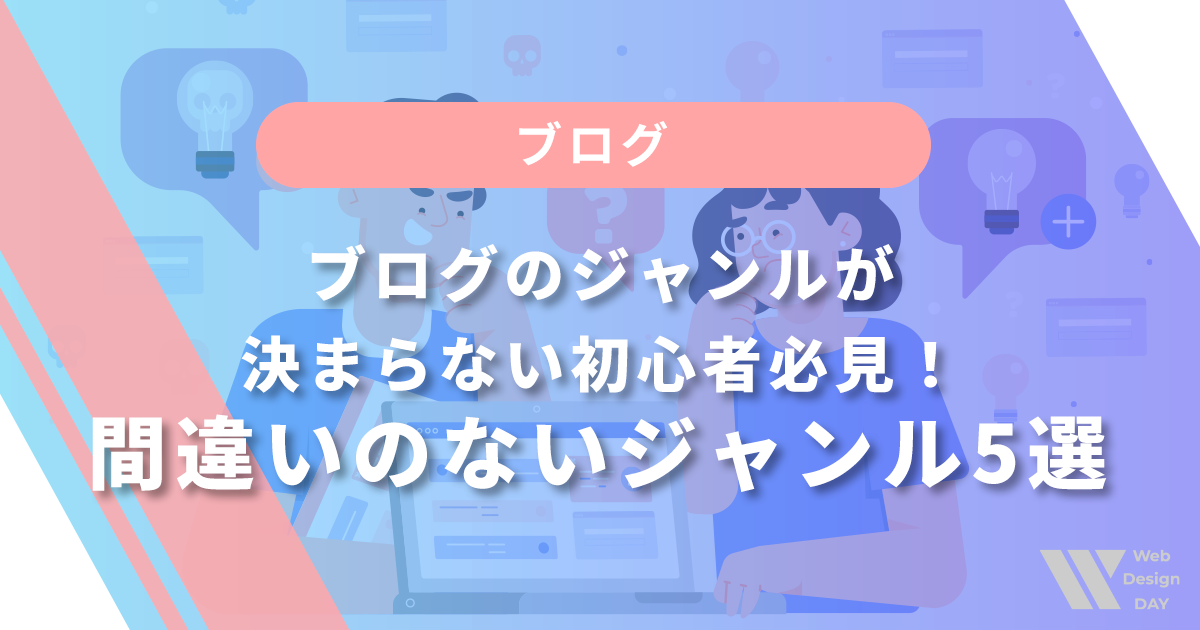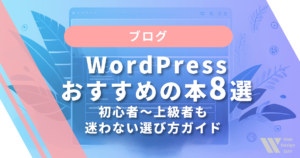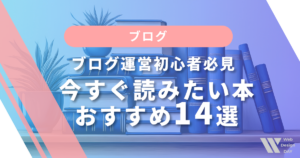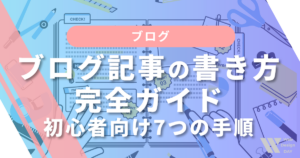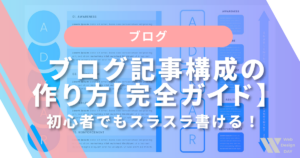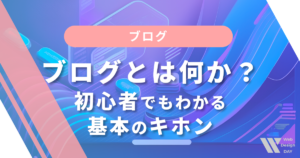ブログを始めようと意気込んでも、「何について書くか」がなかなか決まらない…。
実はこの“ジャンル選び”の壁にぶつかって立ち止まる初心者は非常に多いです。
これを知れば、あなたが前に進めなかった理由が明確になり、安心して次のステップに進めるはずです。
- ブログを始めたいけれど、どのジャンルで書けばいいのか分からずに迷っている初心者の方
- 収益化を目指してブログを始めたいけれど、何をテーマにすれば稼げるのか知りたい方
- 「ジャンル選びで失敗したくない」「これで間違いない」と確信して始めたい慎重派の方
- 既にブログを始めているが、ジャンル選びが正しかったのか自信が持てない方
- 途中で挫折してしまった経験があり、今度こそ継続できるジャンルで再挑戦したい方
なぜブログのジャンルが決まらないのか?
初心者が陥りやすい3つの思考パターン
初心者がジャンルを決められないのは、よくある3つの思考パターンに陥っているからです。
選択肢が多すぎたり、完璧を求めすぎたりすることで、「どれを選んでも不安」という状態に陥ってしまいます。
たとえば以下のようなパターンが多く見られます:
- ①「自分には特別な知識がないから、発信できるジャンルがない」
- ②「好きなことを書きたいけど、それで本当に稼げるか分からない」
- ③「最初から完璧なジャンルを選ばないと失敗しそうで怖い」
これらの思考は、どれも「行動する前に考えすぎてしまう」ことが原因であり、進むべき一歩を見失わせます。
「好きなこと」と「稼げること」の間で揺れる理由
ジャンル選びで迷う大きな理由は、「好き」と「稼げる」が一致しないと感じているからです。
ブログで成功したい気持ちと、自分の興味がかみ合わないと、「どちらを優先すべきか」で悩んでしまいます。
実際、アフィリエイトで収益化しやすいジャンル(金融、美容、健康など)は専門知識が必要なことが多く、書きたいこととはズレがちです。
一方で、自分の趣味や日常をテーマにすると書きやすい反面、「本当に需要があるのか?」という不安に陥ります。
この理想と現実のギャップが、ジャンル決定を複雑にしているのです。
「選ぶ=失敗する可能性がある」と感じてしまう心理
ジャンルを選ぶ行為そのものが、「失敗したくない」という心理ブロックを生みやすくしています。
一度選んでしまうと「もう引き返せない」と思ってしまい、慎重になりすぎてしまうのです。
ブログは継続がカギとなるメディアですが、「ジャンルを間違えたら何ヶ月もムダになる」といった不安を抱える人は多いです。
その結果、選択を先延ばしにし、「どれが正解か」ばかりを探すループにハマってしまいます。
しかし実際には、最初から完璧なジャンルを選ばなくても、修正しながら成長していくことが可能です。
「間違いのない」ジャンルを選ぶ際の5つのポイント
初心者が安心して選べる「間違いのないジャンル」選ぶポイントは以下の5つです。
- 需要がある
- 体験ベースで書ける
- 競合が強すぎない
- 継続しやすいジャンルを選ぶ
- 収益化の導線が作りやすいジャンルを選ぶ
それぞれ詳しく解説します。
① 需要がある
どれだけ質の高い記事を書いても、そのジャンルに興味を持っている人が少なければアクセスは集まりません。
初心者にとっては、まず「検索されているテーマ」であることが重要です。
Googleの検索窓に入力されるキーワードが多いジャンルは、それだけ読者ニーズがあるという証拠。
ラッコキーワードやキーワードプランナーのような無料のツールを活用し、月間検索数が一定以上あるかを調べるだけでも、有望なジャンルかどうかを判断できます。
需要のあるジャンルは、継続的なアクセスと収益につながる可能性が高まります。
ブログのキーワード選定については以下の記事で詳しく解説しています。
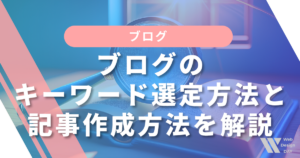
② 体験ベースで書ける
専門知識がなくても、自分の経験をもとにした発信なら、初心者でも十分に価値あるコンテンツが作れます。
たとえば、転職活動や資格勉強、副業へのチャレンジなどは、同じように悩んでいる人の参考になることが多く、共感も得やすいです。
また、体験談はGoogleからも信頼性の高い一次情報と見なされやすく、SEOにも有利に働きます。自分が実際に経験してきたことを言葉にするだけなので、記事を書くハードルも低く、継続にもつながりやすいジャンルです。
また、専門性の高いベテランの人が書くブログから勧められても実感が湧きにくいところもありますが、
同じ立場で奮闘しているブログの人から勧められると「自分もやってみよう!」と思ってもらいやすいです。
 かすが
かすがこのブログも自分の経験を活かした「WEB制作」と、現在挑戦中の「ブログ収益化」の2軸で記事を書いています。
③ 競合が強すぎない
検索結果の上位に企業メディアや専門機関のサイトが多いジャンルは、初心者にとって非常に不利です。
せっかく良い記事を書いても、検索上位に入れなければ読まれることはほとんどありません。
ジャンルを選ぶ際は、実際に狙いたいキーワードで検索し、個人ブログが上位に表示されているかどうかをチェックしましょう。
ライバルが強すぎないジャンルであれば、初心者でも十分に勝機があります。最初はニッチでもいいので、個人が戦える土俵を見つけることが成功への近道です。
また、一見、競合が強いジャンルでも、キーワードや記事の切り口次第で、個人でも勝負できる余地はあります。
以下がその例です。
- 他社との比較記事
- レビュー記事、
- ネガティブなキーワードで訴求する記事
上記の記事は企業が書けない、もしくは書きにくい記事です。このように十分に個人が勝負できるポイントはあります。
他社との比較記事
消費者庁の比較広告のページで冒頭以下の一文があります。
景品表示法第5条は、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。
要は、他者との比較自体は禁止ではないけど、自社商品だけ明らかに優れている紹介はダメですよ!ということですね。
レビュー記事
レビュー記事については、サービスや商品を提供する会社の中の人は、当然悪いことは書きません。
利用者として、体験をもとにメリットもデメリットも正直に伝える記事の方が信頼性も高くなりやすいです。
ネガティブなキーワードで訴求する記事
ネガティブ訴求も企業はできないポイントなのでチャンスがあります。例えば以下のような切り口があります。
- 「(キーワード) 高い」
- 「(キーワード) ひどい」
- 「(キーワード) 効果ない」
あえて購入前の読者の不安をキーワードにして、それを記事内で解消してあげる方法です。
④ 継続しやすいジャンルを選ぶ
どんなに収益性が高いジャンルでも、あなたが興味を持てず、記事を書くのが苦痛になるようでは続きません。
ブログは中長期的に取り組むメディアです。途中で更新が止まってしまえば、どんなに良いジャンルでも成果にはつながりません。
自分が「もっと調べたい」「語りたい」と自然に思えるテーマを選ぶことで、継続が苦にならなくなります。
継続性は結果として記事の質にも影響し、読者の信頼にもつながるため、選ぶ際の非常に重要な判断基準です。
⑤ 収益化の導線が作りやすいジャンルを選ぶ
ただアクセスが集まるだけでは、ブログ収益にはつながりません。
記事の内容と関連性があり、紹介できる商品やサービスがあるジャンルを選ぶことが、収益化への近道です。
副業や資格勉強ジャンルなら、教材・書籍・ツールなど自然に紹介できるものが豊富にあります。
逆に、日記的なテーマは収益化が難しく、アドセンス単価も低いため、収益目的での継続が難しくなります。
収益導線があるかどうかも、初心者が意識すべきポイントです。
改めて、「間違いのない」ジャンルを選ぶ際の5つのポイントをまとめると
- 需要がある
- 体験ベースで書ける
- 競合が強すぎない
- 継続しやすいジャンルを選ぶ
- 収益化の導線が作りやすいジャンルを選ぶ
この5つのポイントを意識してジャンルを探すことが、成功への第一歩です。
始めやすく「間違いないジャンル」ジャンル【5選】



結局どのジャンルなら失敗しないの?
という声は、ブログ初心者の誰もが一度は抱える疑問です。
ここでは、実際に始めやすく成果にもつながりやすい具体的なジャンルを5選、紹介します。
いずれも体験をベースに記事が書きやすく、読者ニーズが明確だからです。
- 副業・スキル習得体験(例:ブログ、動画編集、プログラミング)
- 資格取得・勉強法(例:簿記、TOEIC、宅建など)
- 生活改善・ライフハック(例:節約術、時短家事、シンプルライフ)
- 趣味・ガジェットレビュー(例:読書、スマホアプリ、ガジェット)
- ライフイベント系(例:転職体験、引っ越し、結婚準備)
①副業・スキル習得体験(例:ブログ、動画編集、プログラミング)
自分の学習過程や実践記録をそのまま記事にできるため、専門知識がなくてもOKです。
同じく始めたい人へのリアルな情報は価値が高く、継続もしやすいジャンルです。
②資格取得・勉強法(例:簿記、TOEIC、宅建など)
合格までの体験や勉強方法、使った教材などを共有することで、読者の役に立ちます。
自分の学びと発信が一致するため、記事にしやすく、他人との差別化もしやすいです。
③生活改善・ライフハック(例:節約術、時短家事、シンプルライフ)
日常の中で実践している工夫や考え方を紹介できるため、特別なスキルが不要です。
共感を得やすく、アクセスを集めやすいジャンルとして初心者にも取り組みやすいです。
④趣味・ガジェットレビュー(例:読書、スマホアプリ、ガジェット)
自分が好きで使っているものや体験を紹介するだけでコンテンツになるので、執筆のハードルが低いです。
レビュー記事は検索ニーズが高く、アフィリエイトにもつなげやすいです。
⑤ライフイベント系(例:転職体験、引っ越し、結婚準備)
誰もが経験するイベントをテーマにでき、自分の実体験がそのまま有益な情報になります。
読者の悩みに直結しやすく、感情移入されやすいため、読まれやすいジャンルです。
どれも「誰かの経験談を求めている読者が多く」具体的な悩みや欲求に応える内容になり、アフィリエイトや広告の導線が作りやすいのもおすすめする理由です。
「副業体験」をテーマにした記事は、「副業を始めたい人」に向けて、「サービス比較」や「教材紹介」などへ自然につなげることができます。
このように、「読者の役に立ち、かつ収益化も狙える」のが、これらのジャンルの強みです。SEOに強くするためには、「悩み→解決」の構成で書くことを意識しましょう。
選ばない方がいい3つのジャンル
一方で、初心者にとっては選ばない方がいいジャンルも確実に存在します。
ここでは、失敗や挫折につながりやすいジャンルの共通点を以下の3つに分けて解説します。
- 「YMYL」ジャンル
- 継続が難しいジャンル
- 広告単価が低いジャンル
避けるべき理由を知ることで、選ぶべきジャンルがより明確になり、遠回りせずにブログ成功への道筋が描けるようになります。
それぞれ詳しく解説していきます。
① 「YMYL」ジャンル
YMYL(ワイ・エム・ワイ・エル)とは、「Your Money or Your Life」の略称で、Googleの検索品質ガイドラインに登場する概念です。
これはつまり、「お金や人生に大きな影響を与えるジャンル」のことを指します。
これらのジャンルで間違った情報が広まると、人の健康や財産に悪影響を与える恐れがあるため、Googleは特に正確性・専門性・信頼性(E-E-A-T)を重視しています。
そのため、YMYLに該当するジャンルで検索上位に表示されるのは、病院・大学・大企業などの専門性が高いサイトがほとんどです。
初心者が個人でこの分野に参入しても、記事が読まれる可能性は極めて低く、ブログ初心者が扱うジャンルとしては難易度が非常に高いといえます。
以下のジャンルがその典型です。
- 医療・健康(例:病気の治療法、薬の紹介、健康食品の効果など)
- 金融・投資(例:クレジットカード、株式投資、仮想通貨、保険の比較など)
- 法律・税金(例:離婚手続き、相続、確定申告、起業の法的手続きなど)
- 時事問題(例:政治、社会問題、災害、戦争、国際情勢など)
- 教育(例:子どもの発達、学校選び、教育方針、学習障害など)
医療・健康(例:病気の治療法、薬の紹介、健康食品の効果など)
この分野は人の命や健康に関わるため、Googleは医師や医療機関などの高い専門性を持つ発信者を優先して評価します。
初心者が体験談を書いても検索上位に上がるのは極めて困難ですし、情報の誤りがあるとトラブルの原因になるリスクもあります。
金融・投資(例:クレジットカード、株式投資、仮想通貨、保険の比較など)
金融はお金に直結するジャンルであるため、詐欺や誤解を防ぐ目的から、信頼性の高い法人サイトが優遇されています。
アフィリエイト報酬は高いものの、初心者がこのジャンルで成果を出すのは非常に難しく、検索上位のほぼすべてを企業が占めています。
法律・税金(例:離婚手続き、相続、確定申告、起業の法的手続きなど)
法律に関する誤情報は重大な問題を引き起こす可能性があるため、弁護士事務所や公的機関のサイトが優先されます。
個人が安易に情報発信すると、信頼性の面で大きなハンデがある上、間違った内容を掲載した場合に法的な責任を問われることもあります。
時事問題(例:政治、社会問題、災害、戦争、国際情勢など)
時事問題は、人々の判断や感情に大きな影響を与えるため、Googleは公的機関・報道機関・専門家による正確な情報を重視しています。
特に政治や社会問題に関しては、誤った情報の拡散を防ぐため、個人発信の評価が非常に厳しくなっています。
アクセスを集めやすいテーマではありますが、情報の取り扱いに高い注意が求められるため、初心者がブログジャンルとして扱うのはリスクが高いです。
教育(例:子どもの発達、学校選び、教育方針、学習障害など)
教育は子どもの将来や家族の人生に関わる重大な分野であり、専門家や教育機関の情報が優先されるYMYLジャンルです。
特に発達障害や教育方針などは、親の判断に影響を与えるテーマであり、正確性や信頼性が強く求められます。
個人の体験は一部有益ですが、一般化しすぎると誤解を生むリスクもあるため、初心者が収益目的で扱うには注意が必要です。
② 継続が難しいジャンル
モチベーションが続かない、または自分にとって負担が大きすぎるジャンルは避けるべきです。
続けることが苦痛になってしまうと、ブログ運営が止まり、収益化の前に脱落してしまうからです。
「投資」「医療」「法律」などは情報の正確性が求められ、初心者が書くには調査と勉強のコストが高すぎます。
あまり興味が持てないテーマを「稼げそうだから」という理由で選んでも、継続が難しくなり、結果的に失敗しやすいです。
ブログは長期戦なので、「自分が続けられるか?」の視点は非常に重要です。
③ 広告単価が低いジャンル
広告単価が著しく低いジャンルは、アクセスが集まっても収益化が難しく、初心者には非効率です。
どれだけ記事が読まれても、広告クリックや成約で得られる収益が数円〜数十円程度にしかならないからです。
広告単価が低いジャンルは、大量のアクセスと更新頻度が必要なため、特に初心者が収益目的で取り組むには不向きです。
ブログでひと月の収益目標を30,000円に設定した場合を想定して、どれくらい売れば達成できるか考えてみましょう。
- 30,000円のものを1個売る
- 10,000円のものを3個売る
- 3,000円のものを10個売る
- 1,000円のものを30個売る
- 300円のものを100個売る
どれなら達成できそうと思いましたか?
広告単価の選定も大事な戦略になってきます。



ちなみに私なら、高額過ぎず、低額過ぎない「3,000円のものを10個売る」を目標に選びます!
「このジャンルで大丈夫」と確信するための3ステップ
ジャンルを選んでも、「本当にこれでいいのかな…」という不安が残ることはよくあります。
特に初心者にとっては、その不安が行動を止めてしまう最大の要因です。
このパートでは、ジャンル選びに納得と自信が持てる3つのステップをご紹介します。
感覚ではなく「根拠を持って選ぶ」ことで、「自分の選んだ道でいいんだ」と思えるようになります。
迷いから解放されて、前に進みたい方は必読です。
① 自分の「好き・得意・経験」を棚卸しする
まずは「好き」「得意」「経験のあること」をメモに書き出すことで、無理なく続けられるジャンルの候補が明確になります。
続けられるジャンルは、発信のエネルギー源になります。無理して書くジャンルよりも、自然に情報が湧いてくるテーマがベストです。
英語学習や転職活動、資格試験の記録など、実体験に基づいたテーマは読者の共感も得やすく、書く側も飽きにくいです。
ジャンルを決める前に、まずは「自分の中にすでにあるネタ」に目を向けてみましょう。
② 市場ニーズや競合性をリサーチする
選んだジャンルに「検索される需要があるか」「競合はどれくらい強いか」を事前に調べることで、成功の可能性がぐっと高まります。
需要がないジャンルではアクセスが集まらず、競合が強すぎるジャンルでは埋もれてしまうからです。
Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどの無料ツールを使えば、自分が書こうとしているテーマの月間検索数や関連キーワードを調べることができます。
さらに、実際にそのキーワードで検索し、検索上位が企業サイトばかりなのか、個人ブログもあるのかを確認すれば、競合の強さも判断可能です。
ここで「いけそう!」と感じられたら、そのジャンルは大いにアリです。
③ 小さく始めて、反応を見ながら方向性を固める
最初から完璧なジャンルを選ぼうとするのではなく、まずは試しに記事を書いてみることが重要です。
実際に書いて公開し、アクセスや反応を見てから方向修正すれば、リスクなくジャンルを固めることができるからです。
この方法であれば、「ジャンル選びで失敗したらどうしよう…」という不安を抱えることなく、「実践しながら選ぶ」という柔軟なスタンスで進められます。
ジャンルに迷う初心者が選ぶべき道とは
ここまで、初心者がブログのジャンルで迷う理由や、間違いのないジャンルの選び方について解説してきました。
最後に、ジャンル選びに迷うあなたがこれからどのような行動を取れば良いのかを整理してお伝えします。
「完璧なジャンル選び」より「まず動く」ことが大切
ジャンル選びに100点満点の正解はありません。
それよりも、行動しながら修正していくことの方が重要です。
始めなければ成果も出ず、反応も得られず、何が正解かさえ見えてこないからです。
書きながら見えてくる自分の強みや、読者の反応をもとに軌道修正して成長していくのがブログの本質です。
選んだジャンルが「今のベスト」であるなら、それで十分です。迷い続けるより、まずは書くこと。そこからすべてが始まります。
ブログのジャンルについてのFAQ
まとめ
以下にこの記事のポイントをまとめます。
「間違いのない」ジャンルを選ぶ際の5つのポイント
始めやすい「間違いないジャンル」ジャンル【5選】
選ばない方がいい3つのジャンル
「このジャンルで大丈夫」と確信するための3ステップ
そして、せっかく選んだジャンルにどんな商材があるか、実際にASPに登録して確認してみましょう!
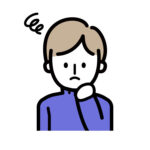
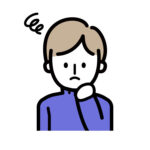
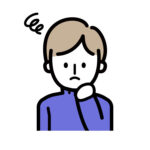
まだ始めたばかりでブログ記事がない…。
そんな方でも、安心です。審査のないASPもありますので、まずはそこから登録してみましょう。
以下の記事で主要なASPを詳しく解説しています。
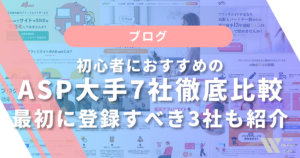
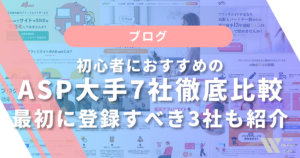



最後まで読んでいただきありがとうございました!以下のおすすめ記事もチェックして見てくださいね!
まだブログを始めていない方は以下の記事をぜひチェック!
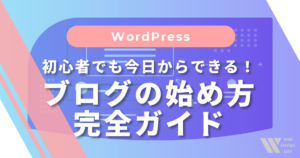
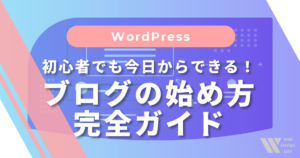
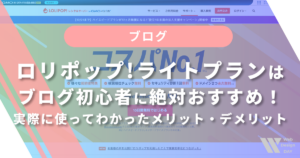
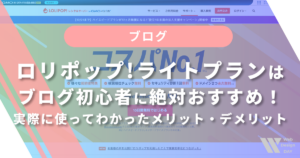
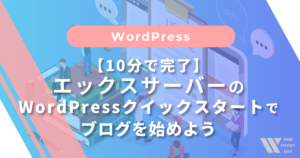
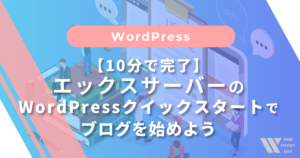
ブログを始めたばかりの人は以下の記事をぜひチェック!